奇妙な世界の片隅でさんの新入生のための海外幻想文学リスト経由で海外文学読書録さんの新入生のための海外現代文学リスト(2018年版)と漂着の浜辺からさんの学生のための海外文学リスト50+4知って、自分も作ってみたくなりました。
といってもすでに6月。新入生向けというにはだいぶ遅い感じですが、そのあたりはとりあえず気にしないことにして、ラノベに飽きた学生向けというテーマでどういう本を選ぶかというのは意外と難しい気もします。ラノベに飽きたというよりもラノベ以外の本はほとんど読んできていなかった人向けのほうが選びやすいかなということでそういう人向けで考えてみました。
次に問題にはなるのはこの手の場合、入手しやすいものを選ぶかどうかという問題ですが図書館もありますし、インターネットなどなかった時代ならともかく、今ならばネット検索すれば後はお財布との相談でなんとかなります。本を読むということはその本を探すというところから、いや正確にいえばその本の存在を知ったところから始まるのではないでしょうか。
ということであえて入手困難な本を中心として7作品ほど選んでみました。
新入生のためのひねくれ文学リスト
1.『キンドレッド 絆の召喚』オクティヴィア・E・バトラー 山口書店
ご先祖様を救え。
主人公はタイムトラベラー。ご先祖さまに命の危険が迫るとき、自分自身の存続を守るために過去にタイムトラベルをし、ご先祖様を助けるのだ。
しかし、主人公は黒人女性。ピンチになるご先祖様のいる時代は奴隷制度のバリバリのアメリカ南部。黒人は許可証なしではひとり歩きもできない時代である。助ける方もピンチだ。というか、ご先祖様よりも私の方がピンチじゃないの!
ご先祖様は私が助けるとして、私のピンチは誰が助けてくれるの。未来から私の子孫は助けに来てくれないの?
なおかつご先祖様は白人の少年。どうやら主人公には白人の血もながれているらしいのだが、それがなにかの助けになるのかといえばまったくない。それどころかご先祖様は差別意識満タンの白人なので助けてもらっても感謝のかの字もない。
タイムトラベルは主人公の意志とは無関係にご先祖さまがピンチになると自動的に発動する。では元の時代に戻る手段はというと、今度は主人公が命の危険にさらされたときなのだ。行くのも地獄、帰るのも地獄。ご先祖様が子孫を残すその日まで主人公はご先祖様を助けるためにタイムトラベルをしなければならない。
2.『信ぜざる者コブナント 破滅の種子』ステファン・ドナルドソン 評論社
主人公はハンセン病患者。転生したら病気も治っていて、魔法も使えるらしくってさらに英雄として奉られている。
「でも、信じない」
この物語が書かれた時代はハンセン病に対する差別がまだ激しかった時代。主人公の家の前には定期的に食料が置かれる。それは町の人の親切心からではなく、主人公が食料を買いに外に出てきてもらっては困るので外に出なくてもすむように食料品を置いていくのだ。で、あるとき主人公は殴られて気絶し、気がつくと異世界に転生していた。
その世界での主人公は健康体で魔法も使えるらしい。魔法の使い方はまだよくわかっていないけれども、魔王に魔の手にかかっているこの世界を救う救世主として奉られる。みんなが英雄として扱ってくれるのでやりたい放題だ。
「でも信じない」
主人公はこれはなにかの間違いだ、これは夢だと決して信じようとしない。信ぜざる者である。
そんな物語が面白くなるのかというと、ギャグのような設定でありながら非常にシリアスで、違う意味で重苦しく面白い。
日本では第三部までしか翻訳されていません。残りの二冊のタイトルは
『信ぜざる者コブナント 邪悪な石の戦い』
『信ぜざる者コブナント たもたれた力』
です。
3.『半球の弔旗』レジス・メサック 牧神社
人類は滅んだ。
生き残ったのは男の子7人、女の子1人。
これが逆だったら男の子のハーレム状態なのだろうけれども、もちろん女の子にとっては逆ハーレム状態なのでそれはそれは楽しい世界になるのかもしれないが、レジス・メサックはそんな話など書かない。
実は大人の男性が一人いて、彼がこの物語の語り手なのだ。じゃあちょっと展開が違うじゃないかと思うかもしれないけれども、この物語は想像の斜め上を行く展開をする。
主人公は家庭教師で生徒たち十数人を引き連れて高山地方の洞窟にピクニックに出かける。その最中に戦争が起こり、人類は滅亡して、主人公と十数人の子供たちだけが生き残ったという設定である。では主人公が大人として子供たちを導いていくのかと思いきやそんなことはしない。主人公はすでに諦めてしまっていて傍観者として子供たちをみているだけである。いっぽう子供たちは子供たちで、自分たちで唯一の女性である女の子を中心とした社会を作り上げていく。女性の方が強いので、女王様とお呼び、の状態である。
さらには導いていく大人がいないので、子供たちの社会は自己中心的だ。女王様の寵愛を受けようとして男の子たちは嫉妬や妬みで殺し合い少しずつ人数が減っていく。
おいおいそれじゃあ人類が滅亡してしまうじゃないかという読者の気持ちなどおかまいなく、彼らは好き勝手に生きていく。彼らにとって人類の滅亡など関係ないのである。
4.『幸せな家族 そしてその頃はやった唄』 鈴木悦夫 偕成社
僕は退屈だったのでみんな殺した。
私も退屈だったのでそんなあなたを陰ながら応援して、そしてあなたを操った。
幸せそうな家族を襲った悲劇。
お父さんが殺され、お兄さんが殺され、お母さんが殺され、友達が殺され、お姉さんが殺され、最後に僕が生き残った。そりゃ犯人は僕だからだ。
ライトノベルの次に読む作品ということだが、この作品は児童小説である。通常は児童小説->ライトノベルという方向に進むのだろうけれども、逆方向に進むのも悪くない。というかこの小説は児童小説の極北に位置しているのでかなり特殊だ。
ミステリ仕立ての物語だが読んでいけば推理しなくっても犯人は予想がつく。意外な動機も面白い、しかし一番の衝撃はラストのお姉さんの手紙だ。家族の愛に満ち溢れているというか姉と弟の禁断の愛が暴露される。読み終えてみるとこの家族がいびつな愛に満ちた家族だったことがわかる。
5.『京城・昭和六十二年―碑銘を求めて』卜鉅一 成甲書房
もしかしたらこれは本当の歴史なのかもしれない。
日本の社会において嫌韓という感情が根強く残っている。一方で外国においても反日という感情が存在している。
この本は伊藤博文が暗殺されなかったとしたら、朝鮮半島の統治は今も続いていたのかもしれないという仮定のもと、今もまだ日本による統治が続いた世界を描いた物語だ。書かれた時代が1987年、つまり昭和62年のことなのでタイトルどおり物語の時代も昭和62年である。
興味深いのはこの物語のどこにも反日という思想が見えてこないということだ。作者は韓国人。登場人物たちはあくまで日本による統治をごく自然に受け入れて、そして平穏に生活をしている。日本の支配によるディストピア化した社会でもなく、かといって今よりも素晴らしい社会でもない。主人公は妻子がありながら部下の女性に恋心をいだいていたり、詩を書くことを趣味としていて作中に自作の詩が差し込まれていたり、アメリカ企業との併合に奮闘したりとごく普通のサラリーマン小説といってもおかしくない物語だ。違うのは統治しているのが日本であるというだけである。ただ韓国という国は存在しない。韓国古来の言葉は完全に消滅しだれもその言葉を知らない。
そんな中、主人公は見知らぬ言葉で書かれた一冊の本と出会う。今は存在しないもう一つの国のことが描かれている。
静かで抑えた筆致でありながら重厚なこの物語は強烈な自己主張をしないがゆえに読み手のほうが考えなくてはならない気持ちにさせてくれる。
6.『しろいくまとくすのき』文 川島誠 絵 長新太 文溪堂
初心に戻って絵本だ。
登場人物は、というか登場するのは動物である。
主人公はまっ白なクマの子供。まっ白で生まれてきたために母親に捨てられひとりで生きてきた。そんな主人公の唯一の友達は、崖から落ちそうになったところを助けたイノシシの子供だけである。
主人公が暮らす森にはクマの仲間たちもいるのだが、白いからだの主人公は仲間に入れてもらえない。
そんなあるとき、人間たちが森を襲ってきた。白いクマはそれまでクマたちと敵対していた狼と協力して人間たちを追い払うことに成功する。大活躍をした白いクマはクマたちに認められ仲間として受け入れられる。しかし、人間の魔の手を防ぎ平和になった森の世界で狼とクマは再び敵対し始め、狼と友達である白いクマはクマたちからのけものにされてしまう。一方で友達だったはずの狼たちからも白いクマはクマたちの仲間とみなされ、友達のイノシシは見せしめに殺され、とうとう白いクマは友達の狼と戦わざるを得ない状況に陥る。
すべてを失った失意のなか、白いクマはクマになんか生まれなければよかったと自己否定する。
友情も努力も共生も、さらには生まれてきたことも否定するとんでもない話だ。
7.『チリの地震-クライスト短篇集』H・V・クライスト 河出書房新社
たった一人でナポレオンの暗殺を企てたり、ゲーテに対抗する劇作家にとなろうとしたりと志だけは高かったけれども、何をやってもうまくいかない人生。最後は愛人の人妻と心中して34歳で亡くなった作家の残した作品。
作品と作者は別物として考えるべきなのだけれども、H・V・クライストの場合は同一に考えてみてもいいんじゃないか、そんな気持ちにさせられる。
表題作の「チリの地震」はタイトル通り、チリで起こった地震の様子を描いたある種のディザスター小説。登場人物たちは虫けらのように死んでいく。何をやってもうまくはいかない。
「拾い子」の主人公は、あまりにも悲劇的な出来事が続いたせいで憎しみの余り殺人を犯すが、教会で告解をすれば罰せられずに済むにも関わらず、告解せずに自ら地獄に堕ちようとする。自分の罪を悔いて地獄へ行くつもりなのかと思いきや、想像の斜め上をいく心情を吐露する。それは、自分が殺した相手が地獄に堕ちたので自分も地獄に堕ち、地獄へ行ってまでも復讐の続きをするためなのだ。あまりにも直情的というか激情的すぎる主人公だ。
次々と意外な展開が続く「決闘」では、どちらの言い分が正しいのか皇帝陛下の命による決闘が行われ、ようやく勝負がつくのだが、負けた方の言い分がものすごい。
「自分は負けたかもしれないが死んではいない、だからまだ決着はついていないのだ。」
負けたと認めない限り、何がどうあっても負けないのだ。ある意味素晴らしい。
「話をしながらだんだんに考えを仕上げてゆくこと」というエッセイでは、なるほど、書きながらとか、話ながら考えがまとまっていくことってあるよねと、読み進めていくと最後にあるのが「未完」という文字で、唖然とする。全然まとまっていないじゃないか。
新入生のためのひねくれ文学リスト
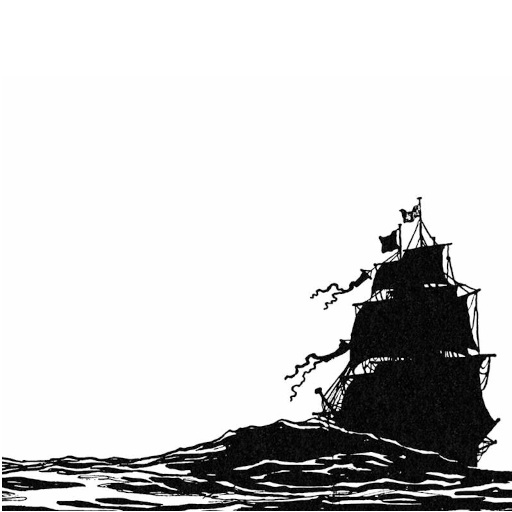

コメント