ブログのタイトルに付けるくらいにコードウェイナー・スミスの小説は好きなんですが、それ以上に好きなのがジャック・ヴァンスの小説です。
国書刊行会の未来の文学第三期のラインナップにジャック・ヴァンス短編集が上がってからというもの、ひたすら待ち続けています。
第三期が始まるためには第二期が完結していなければいけないわけですが、肝心のディレーニイの『ダールグレン』がなかなか出てくれません。しかし、『ダールグレン』がとっとと出てくれないと第三期が始まらないじゃないか早く出やがれこの野郎と祈っていたら、『ダールグレン』は都合により第三期刊行に変わりましたという版元のアナウンスがあって、これはいよいよもって第三期の始まりじゃないか、世の中、祈り続ければ通じるものだと思いました。そして予想外なことに早川書房から『ノパルガース』が出ました。
値段からするとどう見ても『竜を駆る種族』並みの分量としか思えず、そこが不満だったのですが、それでも、大きな活字のトールサイズではなく、小さな活字みっしりのトールサイズという可能性もまったくのゼロとは言い切れないんじゃないかと無謀な期待をしていました。しかし実物を手にとってみて、あまりの薄さとあまりの活字の大きさにがっかり。
がっかりといえば、かつて、伊藤典夫がわざわざ選んで翻訳したのだから本人がBクラスといっておきながらも実は面白いんじゃないだろうかと期待しまくって読んだロバート・リードの『地球間ハイウェイ』がやっぱりその程度だったというトラウマが残っているので、ヴァンスといえども『ノパルガース』もあまり期待出来ない気がします。しかしヴァンスを偏愛する身としては期待するなというほうが無理なのですよ。
で、ネットでの評判はわりと好意的で良いようなんだけどさ……。
実際に読んでみると、うーん、ヴァンスなので文句は何も言わないし、これはこれで面白かったんだけど、何処が面白かったのかというと、なんだか無理矢理よかったところ探しをしているような感じで、なんだか釈然としないのです。
ヴァンス再評価の機運が高まりつつあると知っているんだったら、こんなの訳すよりももっと他に訳すものがあるだろう、伊藤典夫。と文句を言いたくなってきます。まあ、あまりにも我が儘すぎる注文なのはわかっているんですが。
そんなわけだから、『ノパルガース』を読んだ程度では自分の中のジャック・ヴァンス分は足りなくって、これはもう、再読しようと思いつつも二年半以上もほったらかしにしておいた『大いなる惑星』を再読するしか、この心のもやもやは振り払うことができないだろうと思ったのでありました。
で、そんな決心をしながらも再読したのは……。
ハインラインの『夏への扉』だった。
そりゃ仕方がないじゃないですか。
以前にオールタイムベストを選んだときには外していたけれども、私の心の中のオールタイムベストの第一位はいつだって『夏への扉』なのですよ。
それが新訳となって出版されるときたら、万難を排して読むしかないわけで、なにしろあの福島正実訳の『夏への扉』に挑むわけなんだから、たとえ新訳が失敗していても、その心意気だけでもくみ取ってあげたくなるではないですか。
と、言いながらも不安だらけだったのは事実。
何しろ読んだのは28年も昔のことで、それ以降再読はしていません。経験上、再読すればがっかりする可能性は十分に高くって、新訳がどのくらい補ってくれるかということだけなのです。
で、恐る恐る読み始めてみると、ああ、なんということか、これがやっぱり面白いのです。
「文化女中器」は「おそうじガール」と名前を変えていたけれども、そんなものはあまり気にならない。いや、全く気にならないというと嘘になるので「あまり」と書いて置くけれども、そりゃそうだよねえ。
福島正実は、Hired Girlを「文化女中器」と訳して、それに「ハイヤードガール」とルビを振っているのですから。小尾芙佐は「おそうじガール」の「おそうじ」の部分に「ハイヤード」とルビを振っていて、たしかに善戦しているけれども、インパクトの点では負けてしまうのは仕方がないでしょう。
それに、「文化女中機」ではなく「文化女中器」としたのも秀逸じゃないかと思いますよ。動力源があって稼働部品もあるのだろうから「器」じゃまずい気もしますが、「文化女中機」じゃあ駄目だよね。「護民官ピート」と「変幻自在ピート」を比べても、言葉の力強さの差は歴然としているよなあ。
もっとも、だからこそ新訳は新訳で、福島正実の重圧から逃れた小尾芙佐の言葉による新鮮な物語となっているわけであって、再読しても面白かったのです。おそらく福島正実訳を再読していたらここまで楽しめなかったんじゃないでしょうか。
じゃあ、福島正実訳は古びてしまって駄目なのかといえばそんなことはないのです。小尾芙佐訳がどんなに素晴らしくったって、十代の僕が読んで感動したのは福島正実訳のほうなのですから。
そして、たとえ古びてしまっていたとしても僕が福島正実訳を信頼するのは、ラストの一文なのです。
「そしてもちろん、ぼくはピートの肩を持つ。」
相棒の行動が正しいと思ったときは、「正しい」なんて言わずに「肩を持つ」ものだよね。
で、その後にようやくジャック・ヴァンスの『大いなる惑星』を再読したのだけれども、ああ、やっぱり新訳の力というのは大きいものだと実感してしまいましたよ。
25年前の初読時に感じたインパクトの大きさがそれほど感じられなかったのです。いや、最初っから『大いなる惑星』がその程度のレベルだったといえば、その通りかもしれないのですけどね。
記憶に残っている以上に人がバタバタと死んでいく話だったのと、終盤のグロテスクさはやっぱり面白かったのだけれども、再読して満足したかといえば満足しなかったわけで、もやもやは晴れていません。今度は、日本のエースダブルこと、久保書店のSFノベルズ所収の「宇宙の食人植物」でも再読してやろうじゃないか。
『大いなる惑星』を再読してやろうと思ってから実際に再読するまでにずいぶんと長い時間がかかったわけなんですが、長い時間がかかったといえば、前回の記事でも触れた『都筑道夫の読ホリディ』も読み終えるのにずいぶんと時間がかかりました。
上下巻、二段組みで千ページ近い分量だから仕方がないとはいえ、合間に他の本を読みながらの読書だったのでなおさら余計に時間がかかりましたよ。
で、読み終えて実感したのは歳を取ることの難しさでした。
いや、歳を取ることなんて簡単というか何もしなくっても老いていくわけなんだけれども、老いて朽ち果てて行くにしろ、やはり理想とする朽ち果てかたというのがあって、その理想のとおりに歳を取っていくのは困難なのだよなあと、この本を読みながらその困難さが身にしみたのであります。
上巻で都筑道夫は、歳を取って長い話を読むのが大変な作業になったと言いつつもそれなりに長い話を読んではいたのですが、下巻に入って、急速に老いていくのです。
連載終盤では、スティーブン・キングの『スタンド』が長すぎて読むことが出来ないといい、他の本を読みます。そうこうしているうちに『読ホリディ』の連載は中断。氏が亡くなるのはそれからおよそ一年と数ヶ月後のことでした。
亡くなるまでの間に、都筑道夫は『スタンド』を読むことが出来たのでしょうか。ちょっと気になりました。
気になったといえば、前回の記事であれこれ書いた、マキャモンの『ブルーワールド』の序文の問題に関してですが、現物を手に入れることができたので、さっそくどんな風に訳されているのか読んでみたら、「実の父親」と訳されていました。
これは確かに、文面通り受け取ってしまってもおかしくはないよなあ。
で、誰がこの本を訳したのだろうかと思って表紙を見直したら……。
小尾芙佐だった。
もっとも、序文なので小尾芙佐自身が訳したとは限りませんが。
2009/08/14-2009/08/31
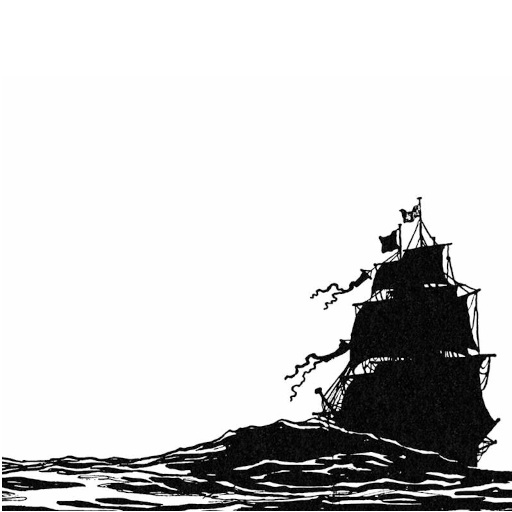


コメント